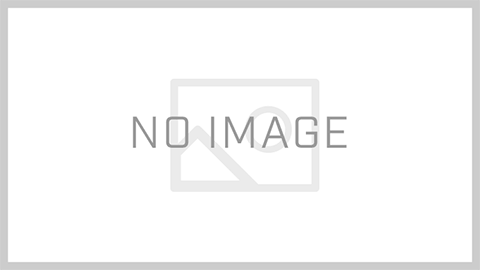こんにちは、あさみんです。
先日、川越の縁側・ちゃぶ台お着物やの縁ちゃぶさんのパーソナルカラー診断を受けてきました。
講師のカラーコンサルタント岩崎沙織さんのブログはこちらから見れます。
当日の様子はこんな感じ
その時に男物の浴衣を着て、意外と好評だったので、女性の私が男物を着る時に工夫したことや気を付けたことをまとめてみました。
なぜ、男物の浴衣?
疑問に思いますよね。
着物・浴衣を着る=女物をイメージする人が多いのではないでしょうか?
男物の浴衣を着ようと思ったのは、今年のお祭りが中止になってしまったからです。
法被に角帯が締められなかったのが残念で男物の浴衣で今回のイベントに参加してみました。

男性でも細身すぎて帯が上がってしまう人や緩んでしまう人、コスプレなどで男装をする人など参考になるかもしれないのでよかったら読んでみてください。
目次
夏着物や浴衣のインナーは、エアリズムがオススメ!
夏に浴衣や着物を着る時、インナ―困りませんか?
私は、夏場着物に着る時は着物用の肌着ではなくユニクロのエアリズムを愛用しています。
UネックT(半袖)とワイヤレスブラにステテコが夏の定番のインナーセット。
UネックTで脇汗も吸い取ってくれて、胸もボリュムアップせずに支えてくれるので重宝しています。
男物の浴衣や着物は、胸元が空いているので、1サイズ大きめのUネックのT(半袖)がおすすめです。
女物を着る時は、Uネックを前後ろ逆にすると襟を抜いても見えずらいのでよかったら試してみてくださいね。
最近だと、キュロットペチコートも出ているので、裾除け代わりになりそうです。
夏場の屋内イベントでも快適に過ごせたのでエアリズムセットは是非一度試してくて下さい。
男物の浴衣を選ぶときは、試着が大事。上半身のフィット感を確認しよう。
今回着た浴衣は、祖父のお古。
帯を締めない状態で床につくかつかないかの長さでした。
丈はちょうどよくても、肩や胸板の厚みがない為、どうしても上半身はぶかぶかしがちになります。
胸がふくよかな人は大丈夫かもしれませんが、控えめな人の場合は、浴衣でも試着した方がいいかもしれません。
角帯がずり上がらないコツは締める位置。意識する2つのポイント
浴衣は、着慣れないと、帯が上がってきませんか?
いや、女性で男性の浴衣を着たことある人の方が少ないかな?
若い時に撮っていたお祭りの写真は、角帯が上に上がっているものが結構ありました。

この写真は、動くほどにウエストに上がってしまう位置で帯を締めていますね。
白い帯の締める位置が高すぎる。
私が角帯を締める時に気をつけてるポイントは2つです。
- 浮き輪の下に締めて浮き輪を乗せる
- 腰痛ベルトの位置に巻く
20年くらい祭りに参加していると激しく動いても帯がずれにくい位置がなんとなくわかるようなります。
ポイント1 浮き輪の下に締めて浮き輪を乗せる
女性だと浮き輪と聞いたら分かる人が多いかと思いますが、あのお腹周りにつくお肉の下に締めるイメージです。

良い位置に締められたら浮き輪が乗りやすいです。

腰回りのにっくきお肉をしっかりつかめたら位置は大丈夫。
角帯を締めて、浮き輪を乗せると男性ほどではありませんが、恰幅の良い感じになれます。
ポイント2 骨盤ベルトの位置に締める
産後に使うものですがイメージすやすいように例えてみました。
帯の下線が恥骨の上、帯の上線が腰の出っ張った骨の下になるような位置で締めています。

足の付け根の大腿骨がぎゅっと締まるような感じになります。
もし帯が上がってきたら、位置が高すぎの可能性があります。
レディス物のボクサーパンツのゴムの高さと覚えておくといいかもしれません。
何回か締める練習すると、ずれない位置がつかめてくるので是非練習してみてください。
カッコイイ雰囲気のコツは姿勢。意識する3つのポイント
自分では意識していなかったのですが、いつもと全然雰囲気が違ったそうです。
お店に入ってきたときに私と分からないくらいだったみたい。
男物の着る時は、祭りモードの雰囲気だったので、いつもと違うポイントは何だろう?と探してみました。

祭りモードの雰囲気の秘訣は姿勢。私の意識していたポイントは3つ。
- 肩幅で片足重心にならないように
- 肩は開いて反りすぎない
- あたまからつられているように
ポイント1 肩幅で片足重心にならないように
立ち方は、私の場合両足重心で立っています。
肩幅で片足重心にならない様に骨盤を立てている感じです。いわゆる仁王立ちみたいな感じです。
お祭りで、他の地区の山車が来るのを腕を組んで待っている時の姿勢に似ている気がします。
女性の着物だと、出来るだけ足をそろえたり、内股を心掛けているので全然雰囲気が変わります。
ポイント2 肩は開いて反りすぎない
こちらも山車を見上げたりする姿勢に似ている気がします。
巻き肩が一時的でも正しい位置に戻ると背中から見ても凛としているように見える気がします。
着物を着ると帯で骨盤が固定されるから背筋が伸びるのかもしれないと感じました。
ポイント3 頭からつられているように
足元、骨盤、上半身とまっすぐに意識してきて最後は頭。
頭もバランスよく1本の糸でつられているように意識した方が凛とした感じになるような気がします。
姿勢が悪くなりやすい人には、帽子をかぶると意識しやすいのでおすすめです。
小物遊びは、着物遊びの楽しみの1つ
さて、着物が着れて雰囲気の作り方もわかり、このままでも十分出かけられる状態になります。
扇子と巾着を持てば、ふらっと遊びに行けるのですが、やっぱり小物で遊びたくなってしまう。
女物の着物よりも小物遊びの幅が少ないので、今回はカンカン帽を被って出かけました。
他にも、小物遊び出来そうなものを紹介していきます。

最近お気に入りのブローチ
大泉学園のcafeMofreeさんで開催されている三毛猫展で展示販売していました。googlemap
他の遊び方だと、中折れハットにブローチも面白いかなと思います。

クリーム色がどんなリボンの色にも合わせやすいです。
音色にかけて、カラーバリエーションを増やして通販サイトでも販売しています。よかったら覗いてみてください。

最後に、秋に向けて紹介したい羽織クリップは、トルソーさんに身につけてもらいました。

男女兼用できるようにちょっと長めに作ってあります。
近くで見るとチェコビーズがキラキラ。

袴の様な色味の海老茶、ナンド、草色の3色です。
通販サイトには、男性着物、女性着物で身につけている写真を乗せました。
コーディネートの参考に是非覗いてみてください。
着物コーディネートの楽しみ方は人それぞれ
私が初めて男物の浴衣を着たのは、着画取りをしようと思った時でした。
頼める男友達がいないから、自分がモデルになって自分で撮ったのがきっかけです。
人がいないなら自分でやるしかないなぁ~という感じでした。

その時は、角帯にかんざしという使い方を提案したかったみたい。
私にとって女着物と男着物の違いは、デザインの違いという認識なんですよね。
正絹や綿やの素材を違うデザインにした。
ただそれだけ。
洋服だとみんな好きなデザインの服を着ていると思うんです。
身体が小さくて、大人向けの向けの物が大きかったら子供服を買って着ている人。
メンズ向けでもいいと思ったらメンズやユニセックスの服を買って着ている人。
浴衣もそんな認識だったので今回周りの反応に驚きました。
いつもとデザインの違う着物を着たくらいの感覚
「法被着れなかったから男着物で角帯締めるぞ!=スカートじゃなくてズボン履こう」くらいの感覚でした
実は、今回男着物を着て外出したのが初めて。
お店に入った時、店員さんが一瞬動きが止まったような感じかして、戸惑わせてしまったかもしれません。
観光地で外国の人が着物着ている=観光でレンタルしているのかもしれない。
男浴衣着たお客さんが女性の声で「3名でおねがいしま~す」と言われたら、場慣れしていない限り頭が混乱すると思いました。
今までは、男性用の浴衣を女性が着ることは少なかったかもしれません。
最近は、性別問わず、自分の気持ちにとって心地よい服装を着ている人が多いと思います。
着物や浴衣もその服装の1つ。
今年はお祭りが中止になっている地域が多いけど、来年こそは男物の浴衣を着たかった人がパートナーさんと楽しめるといいな
大切な人と楽しい時間を沢山過ごせますように
ここまで読んでくださりありがとうございました。
良かったらまたこのブログに遊びに来てください。
SNSでブログの更新情報も発信していきますのでフォローしてもらえると嬉しいです。
水引などのハンドメイド制作と着物遊びの投稿がおおく、
Twitterは、着物の仲間が出来そうなイベント情報やお出かけ写真を発信しています。
instagramのほうが、コーディネートー写真が多目です。
ふらっと着物を着て遊びませんか?